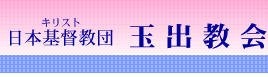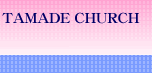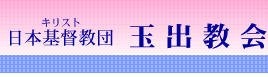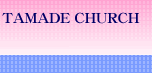聖霊降臨節第五主日、讃美歌14,256,290、交読文19(詩84篇)
聖書日課 ミカ4:1〜7、ヘブライ12:18〜29、ヨハネ4:5〜26、詩編84:2〜13、
早いものです。今年も6月、梅雨入り。例年より一週間近く早いとのこと。
中国の詩人は『年々歳々花相似たり』と詠いました。当時の自然界は時を定めたように動いていたのでしょう。この頃は規則性をかなり無視して、時ならぬ動きを見せてくれます。
人間の側で勝手に、こんなものだろう、と考えるしかないのでしょうか。諦めにも似ています。
昨日夕刻、たくさんのカラスの鳴き声に悩まされました。窓をあけてあるのですが、そのすぐ外で大きな鳴き声が聞こえます。はじめは、関係ない、と考えていました。それにしても随分集まっているようだ、何事か、と思うようになり、外へ出て、見上げました。関係が大有りでした。庭の枇杷の木から飛び立って行きます。中には実を咥えているものもいます。カラスは悪食、なんでも食べる雑食性の鳥、と承知していました。それでも枇杷を食べるとは気付きませんでした。十年以上前のことです。学校の三階の教室で授業をしていると、外でカラスの鳴き声がします。ギャーギャーうるさいので生徒も気にします。窓を開けました。なんと五・六羽のカラスがたった一羽のスズメをいじめていました。とうとう殺してしまいました。それ以来カラスを怖がるようになっています。
怖いもの見たさでしょうか、カラスが何をするか、暫く外に立っていました。カラスは周辺の高い所にとまって様子を見ています。人間を見張っているのでしょう。そのうちにスズメがやってきました。カラスを敬遠していたようです。私が室内に入るとまたカラスの世界。夕暮れが迫ると、一羽また一羽とカラスも巣へ帰ったのでしょうか、ようやく静かになりました。後には、空っぽの枇杷の木が残っているだけでした。
創世記は、35章でベテルにおけるヤコブを描きました。その16節以下には「ラケルの死」が記されます。ベテルを旅立つヤコブの一族、目的地はエフラタとされます。これは今日のベツレヘムです。これは最終の目的地ではなく、キルヤト・アルバ、今日のヘブロンへ向かう途中の地であり、一行のうちの一人ラケルにとって「終の棲家」となった所です。
ラケルはヤコブ最愛の妻でした。彼女はヨハネを生みました。そして今、もう一人を産もうとしています。ヤコブの十二人目の子どもとなる新しい命が産まれ出ました。その代わりのように、ラケルはその命を取り去られます。最後の息の中から、この男の子に名を付けます。
ベン・オニ、私の苦しみの子、という意味です。父親のヤコブはその名を変えます。
ベニヤミン、幸いの子、語根は同じですが読みを変えて、という意味にしました。それは、この子の先行きに対する配慮です。そして、同時にラケルに対する深い愛情の現われでもあります。
ラケルの墓はベツレヘムに設けられました。ヘブロンに下る街道の東側、エルサレムをはるかに望む丘がその所、ラマト・ラヘル、ラケルの丘と呼ばれます。40年近く前、そこにはユース・ホステルがありました。ヤコブの時代、イスラエルとエルサレムとは何の関係もありません。やがてダビデが王国を統一した時、南北の中間に位置するこの町を王都とします。ヤコブはそのようなことになるとは露知らず、この丘にラケルの憩いの地を定めました。深い愛情から出ることは、しばしば神の計画と合致します。ヤコブの名、即ちイスラエルをもって呼ばれる民族国家の首都を見守る最適の場所となります。
35章は、イサクの死をもって幕を閉じます。二人の息子によって葬られました。終わりよければすべて良し、であるなら、イサクの生涯は幸せであったのでしょう。これまでは波乱に富んだものでした。振り返って見ましょう。
彼はアブラハムとサラの夫婦のかけがえのない独り子でした。この約束の子は、与えたもうた神によって、犠牲として捧げるように求められました。アブラハムがナイフを振り下ろそうとした、その時神がその手をとどめ、代わりの捧げものを示されました。この身も凍るような恐怖の瞬間を経験したイサクです。創世記を読み進んで行くとき、このイサクは、陰が薄いように、私は感じます。母の死後、リベカを得て慰めを得た、と記されています。
イサクは、父であるアブラハムが自分を愛しているだろうか、と疑ったことでしょう。
愛されている確信がもてない、これは外からはうかがい知ることの出来ない苦しみです。
最も大きな問題は、愛することが出来ない、ということです。愛は自然に産まれ出る、と箴言や雅歌の詩人は歌います。それをどの様に育て、相手に向けるか、ということは学んで身につけます。愛されて初めて愛することを知るのです。
イサクは父に親しめないものを感じていたのではないでしょうか。自分よりも神様への信仰のほうが大事なのだよ、と感じていたように思います。これはわたしの家族が感じているかもしれないことです。
ヤコブはエサウの双子の弟でした。
父はイサク、母はリベカ。祖父母に当たるアブラハムとサラは、イサクのために、遠くパダンアラムのハラン、サラの故郷に嫁を求めました。信頼できるものが派遣され探し当てられたのがリベカです。はるばる旅をして到着したリベカを見たイサクは、母を失った後の心がようやく慰められた、と記されました。二人は相思相愛であったと感じます。そのような書き方です。
ところが、この二人に双子の男の子が与えられると、二人の間に一致とか、協力は見られなくなってしまいます。子供を育てる時、一番大切なことのはずですが見られません。二人はそれぞれが、エサウを、ヤコブを愛しました。イサクはエサウを愛した、という時、好みの肉を持ってくることが理由と記されます。持って来ないヤコブへの愛は少なかった、ということが示唆されます。リベカは天幕に居てお手伝いをするヤコブを愛した、という時、いつも野山を駆け巡るエサウにはその愛は少ししか注がれなかった。その理由は、愛する側の都合です。どちらが自分に利得をもたらしてくれるか、という計算でした。
妻であり、母であるリベカは、自分が可愛く思うヤコブに長子の祝福を得させるために、夫イサクを騙すよう息子を導きます。これは、リベカが自分の将来を考え計ったものである、と学者は言います。族長イサクの物語の特徴は、自己中心的な、利益を求める愛が語られていることである、と考えます。
これをイサク・リベカの偏愛、偏った愛と申し上げました。
偏愛の結果、ヤコブは兄エサウを怒らせてしまい、逃げ出すこととなりました。リベカは、暫くの間だけ、ハランへ行きなさい、と考えました。その暫くは、大変長い間となります。間もなく再会するはずでした。20年が過ぎ、ヤコブがカナンの地へ帰ってきた時、リベカの姿はありませんでした。
家族を愛する時、愛情は均等に注がれることが必要です。不平等に注がれる時、競争が発生します。良い競争があることは、誰も否定出来ません。しかし愛を求める競争は悲劇を生み出します。自分が愛されていない、と感じるようなことはしないほうが賢いでしょう。愛の不足、それを補完するのはただ愛のみです。旧約から新約への大きな流れは、イエス・キリストにおける神の愛が、全ての者に等しく注がれ、それによって全ての人は、まことの愛を知るようになる、ということです。
36章は、エサウすなわちエドム一族の系図になります。エドムは、死海の東南の地名で、その地の住民の名でもあります。後のイスラエル民族は、このエドムの住人とは仲良しではなく、野蛮人として軽蔑していたようです。そのために近縁でありながらイスラエルとエドムは対立することが多かったようです。むしろ、近縁であるからこそ排除しあっていたのかもしれません。
エドム人は、イスラエルがまだ王国になる以前から、王国になっていました。
民数記20:14では、モーセがエドムの王に使者を派遣しています。領土内の通過を願いますが、拒絶され他に向かいました。こうしたことも憎しみの原因になり、後世の人がエドム嫌いになって行くのでしょう。
また、サムエル記上8章でイスラエルの人々は、年老いたサムエルの跡継ぎの息子たちが、裁きを曲げるので、「他の国々のように、我われを裁く王を、我われのために立ててください」と願います。この国々の中にエドムが入っていることは確かでしょう。
王国を形成することが民族の進歩、先進性であるとするなら、イスラエルは確かに当時の諸民族に遅れを取っています。唯一の神を統治者として、貴族階級などを持たないほうが進歩的である、と考えることも出来るはずです。信仰面からも同様に考えます。
37章は、「ヨセフの夢」という小見出しです。夢に入る前に、ヨセフが兄弟の中で特別大事にされていたことに注目しましょう。3節にそのことが記されています。
ここからヤコブはイスラエルと呼ばれるようになります。「イスラエルはヨセフを可愛がり、裾の長い晴れ着を作ってやった」とあります。晴れ着というよりは、裕福な人たちが着る「裾の長い長袖の衣」のことでしょう。兄弟たちが膝丈の労働着や少年用の衣を着ているときに、11番目の子供が働かないで良いような待遇を受けていたのです。兄たちの様子を父に告げていたことも語られています。
この理由は、年寄り子だから、ということで片付けることは出来ません。ヨセフの母は、ヤコブ最愛のラケルでした。すでになくなっていました。愛するものの忘れ形見だから、誰よりも可愛かったのでしょう。ヤコブはヨセフを可愛がりました。自分の利得を求めたものではないが、自分の心に適う故に可愛がります。それだけで兄弟はヨセフを自分たちの仲間にすることが出来ませんでした。そして、この偏愛の結果、家族・兄弟間の睦まじい仲は崩れます。ヤコブは、自分が愛されたようにしか愛することが出来なかったのでしょう。
そのような状況で、ヨセフは夢を見ます。夢には意味がある、と知られていました。
畑で兄さんたちの麦の束が、私の束にひれ伏します。兄たちは、それをヨセフが我われの王になることだ、と解釈します。
太陽と月と十一の星が私にひれ伏します。この夢は父にも告げられます。イスラエルはヨセフを叱ります。「わたしも、お母さんも兄さんたちもお前の前に行って、地面にひれ伏すというのか」。これが夢の解釈でした。すでにラケルは死んで葬られました。母親が上げられているのは、レアの存在、兄たちの母親を意識してのことでしょう。
兄たちはヨセフを妬んだ、と記されますが、むしろ憎んだというべきでしょう。同じことをヤコブ・イスラエルはどの様に感じ、考えたでしょうか。「父はこのことを心に留めた」とあります。現時点で理解しがたいこと、不可解なことに対する、賢明な態度です。
ルカ福音書は降誕物語の中で、おとめマリヤが「これらの出来事をすべて心に納めて、思い巡らしていた」と語ります(2:19)。祝福の始まりです。
創世記全体も、その神と人の壮大なドラマを思い巡らすことを求めています。その遥かな末に神の力と祝福が現れてきます。讃美しましょう。