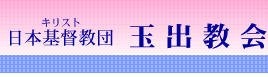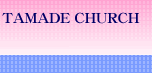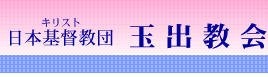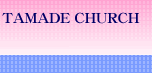父親のテラに伴われてカルデヤのウルを旅立ったアブラム、カナンを目指していることは知っていただろう。しかし、それがどのような理由によるものかは知らなかったのではないだろうか。
聖書を読むとき、人は誰でも主観を完全に排除することは出来ない。出来るだけ客観的に、と考えても主観が強く出てしまうことがある。たとえばこのところ、父親の意図を長男が知っていたかどうか、という問題。これを考えるとき、私は誰にもそのことの理由を完全には説明していないから、アブラムもそうだっただろう、と考えるのは、私自身の生活暦からの主観です。これだけの大移動なら、説明責任を果たしているはずだ、と言う考えもあるでしょう。相談して、多数決をとった、と考えるかもしれません。
「連れて向かった」という言葉を正しく理解するなら、テラの指導制を見るべきです。
アブラムには幾つかの選択肢があったはずです。故郷ウルへ帰る道、そこでは都市生活の楽しみが待っています。友人たちも居るでしょう。何よりも海の幸が待っています。
このハランの地に止まることも出来ました。到着以来どれほどの時間が経っているのか判りません。それなりの交わりがあり、親しさを感じる者たちも居たことでしょう。
それともいっそ、もっと離れた新しい道を選ぶことも出来ます。都市で蓄えた富を持っています。何処へ行っても、それなりの土地を手に入れ、新しい生活を始めることが出来るでしょう。
テラは死んだ、との記述から、この12章の始まりまでには、ある程度の時間が必要であったろうと考えます。一人の人が死ぬとどれ程多くのことが起こってくるか、私たちの多くが経験しているはずです。そしてその中で本当に親身になってお世話をしてくれる方、悲しみを分かち、苦しみを担い、慰め励ましてくださる方と出会うことも出来ました。そうした中で、人はその人の生涯の意味について考えるものです。
アブラムもこの期間に父親のテラは何を考えていたのか、自分の人生について何を基準としていたのか、などと考えたに違いありません。
いろいろ考えながら、今後どのようにするか決めようとするのです。
この地に止まるか、それとも旅立つか。旅立つなら何処へ、父が目指したカナンへ、出発地のウルへ、第三の場所を目指すか。この決定に役立つのは、自分の持っている基準です。
無原則に決めるのではありません。父親がカナン目指してウルを出発した時の基準を息子であるアブラムも共有しようとします。分かち合おうとするのです。
私たちには、聖書は何も告げていませんでした。ただ31節に記されているだけのことでした。「アブラム、ロト、サライを連れて、カルデヤのウルを出発し、カナン地方へ向かった」。もう一度考えましょう。テラは何故旅立ったのか。
何故、当時繁栄する大都市ウルを捨てたのか、何故旅立ち、なぜカナンを目指したのか。
本来農耕民であり、羊の群れを飼う人々でありました。ノアの末裔です。彼らは唯一の神を礼拝する民でした。都市生活は、唯一の神を礼拝することとは遠いものでした。彼らは虚栄と虚飾の民でした。これは、繁栄するダビデ・ソロモンの帝国に対する警告です。ノアの末裔にとってこの生活は、洪水の前の生活の復元であって、ここへやって来たのは何故か、と問うべきでしょう。父テラは、自分にとって非本来的な生活と考えても、敢えてこの地へとやってきました。なにがそれを可能にするでしょうか?
言うまでもありません。この地での生活が、神に命じられたものだからです。それ以外にこの地での生活を可能にするものはありません。これは話し合いで決めることではありません。神から決定として伝えられ、それに従う類のことでした。アブラムは、ウルへ来る時のことは知らないでしょう。彼らにとってここは故郷になっていました。しかし旅立ちのときに、この力に満ちたもう神の存在と、父がこの神の決定に従う姿を見て知ったのです。この家の基準、この家の主は唯一の神である、と彼はしっかり知ることが出来ました。その神の顕れも、何時のことであるか、われわれが知ることは出来ない。我々の都合ではなく、待っているなら、神の側から語りかけたもう、ということも知ったのです。
テラとアブラムの父子関係は、何も語られていません。しかし考えれば考えるほど深みあるもののように思えます。父親は、あまり物を言わなかったかもしれない。しかし息子に、自分が従っている主なる神はしっかりと伝えている。自分の生活には、この神という基準がある、と伝わっているのです。子は親の背を見て育つ、と言います。アブラムは、神に従う父テラの背を見て、きちんと育ったのです。親にとって、子どもが自分の仕事の後を継いでくれる事が喜びになるのは、このような理由があるためでしょう。同じ基準を受け入れてくれる喜び。それは夫婦の間では必須のことでしょう。ひとつの神をひとつの家庭の主と仰ぐことが出来たら、これに過ぐる喜びはないはずです。
テラの死後、アブラムは、動き出そうとしてはいません。テラが、ウルで時が満ちるのを待ったように、アブラムも待ちます。時とは、神が語り、示したもうその時です。
われわれの知らない、神の時が満ちました。それが第1節です。
「ヤハウェはアブラムに言った」。
ここで語られる神の言葉は、アブラムにとってはテラ以来、ある種馴染みのあるものだったのでしょう。家庭教育の実り、結実である、と私は考えます。驚くべき内容ですが、父テラと全く同様に決然として聴き従います。
「生まれ故郷、父の家を離れて」、「あなたの地、あなたの親族、あなたの父の家を出て」、
容易ならざる言葉です。何処の国、どの民族にとっても故郷を離れると言うことは容易なことではありません。一極集中型のこの国では、多くの人が東京志向です。関西弁を使うことに拘りながら、定年後の居住地はそのまま東京にする人が多いのです。それはそのことに利益があるから、また事情が出来ているのでしょう。憧れがある時は故郷を離れます。
止むを得ない時、故郷を離れる心は歌となります。演歌の世界、ドイツリートなど。
司馬遼太郎は「故郷忘じがたく候」と題して一編の小説を書きました。これは、16世紀に秀吉が起こしたおろかな朝鮮戦争のとき、鹿児島へ連れてこられた陶工(焼き物つくり)たちを描いたものです。現在も薩摩焼窯元沈寿官として続いています。
忘れがたく、離れ難い故郷を、アブラムは神の言葉のままに、いとも簡単に立ち去るのです。聖書はそこに何があったか、何も書いてくれないのです。東京集会の松橋さんが所属する蒔田教会の今橋牧師は、「この場面には多くのことがあったはずだ、しかし一瞬の決断だけが記されている」書きました。そうなのです。聖書記者は、省略の名人です。そして集中させるのです。旅立ちの準備、別離の悲しさ、そのようなことを一切書かないことによって、アブラムの決断が如何に非常なものであるか示そうとするのです。情け知らず、ではありません。常ならざることである、という非常です。
「私が示す地に行きなさい」。後に出エジプトのモーセが、同じように行く道を示されながらさすらうことになります。方角としては示されても具体性がありません。それでもアブラムは出発するのです。夫々ご自分のことに置き換えて、お考えになってみてください。
私のことで申し上げると、多過ぎますので止めましょう。
アブラムは、神の言葉を聴かなかった事にすることも出来ました。自分にとって都合の良い言葉を待つことも出来ました。しかし、神の言葉として受け入れました。自分にとって都合の悪い方を選ぶとき、たいていの場合、神様のみ心に適うものなのです。今は、そのことが理解できないことが多いでしょう。10年経つとその御心が判るものです。
神の御心を先ず第一として、自分のご都合は二の次、三の次とすることが出来るようだと、世の中、もっと変わりそうです。ある牧師は説教しました。本当に心から祈るものが十人居れば、そこから何かが変わるよ、世の中を動かすことが出来るよ。
アブラムは、神の言葉を待ちました。アブラムの中に聴き従う姿勢が整った時に、神はアブラムに語られました。それでも彼は、即断はしなかったでしょう。長い沈思黙考、そして一瞬の決断、一歩を踏み出します。世界を変える一歩となりました。
私たち一人びとりが、神の御用に用いられようとしているのです。
ひとあし一足の決断に備えてゆきたいものです。
欄外
故郷を離るる歌、ムシデン ムシデン、水車小屋の娘、冬の旅、
沈寿官、あなたが36年を言うなら、私は370年を言わねばならない。
アブラムがハランを出たとき、テラは生きていた。145才のはず。数字の間違いは良くあること。サマリア五書は、テラは145歳で死んだ、と整理している。なぞが残る数字であるが、テラの死後出発した、というのが自然な読み方である。